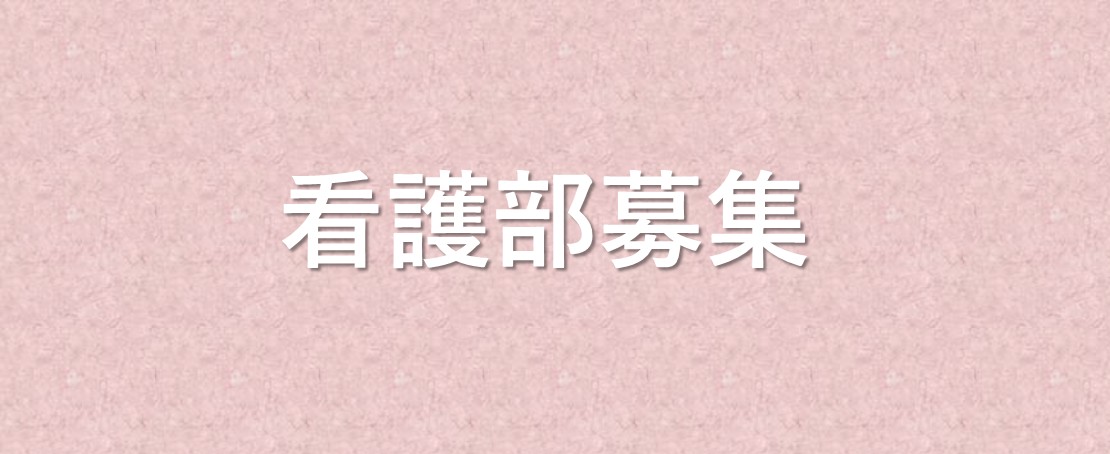私が看護師として、みどり病院3階病棟に配属となり3年が経ちました。この病棟の特徴は地域包括ケア病棟であることです。地域包括ケア病棟とは急性期治療を経過し、病状が安定しているが退院の準備が困難で入院が余儀なくされた患者さんに対して、在宅復帰に向けた支援や準備を目的とした病棟です。入院期限は最長60日までと決まっています。
当院は緊急入院など急性期の患者さんを受け入れることもありますが入院期限は変わりません。限られた期間の中で退院支援をしていく重要性や、早めに取り組んでいく必要性を実感しています。
入院前後でADLが著しく低下する患者さんも多くいます。入院前のADLと比較しながら今後の退院先は元の場所(自宅?施設?)で良いのか見当していくことや、介護保険の申請又は変更は必要か、など考えなければなりません。
当院に勤めるまでは私は急性期病院で働いていたので、ADLが自立している患者さんはそのまま自宅に退院、難しい人はリハビリテーション目的での転院が多かったです。他職種と関わる機会もあまりなかったので退院支援に関して地域連携スタッフにお任せしていました。
介護保険の申請または変更や、自宅退院が困難だからとすぐに入所できる施設を探すことはすぐにはできません。認定調査をしても結果が出るのに数週間はかかるので入院期限がある地域包括では退院支援を早めに取り組むことを意識しなければならないです。コツコツと看護サマリーを更新していく、包括期限をこまめにチェックする、患者さんの家族が面会に来たらお話をするなど心がけるようにしています。
自宅に退院する患者さんでも自宅での生活が今まで通りできるのか、内服などの管理方法など考慮して入院中からアプローチする必要があります。担当の地域連携スタッフに相談することも多くなり、他職種と情報を共有することは大切だと感じました。
毎週1回退院支援カンファレンスを行っており、退院支援が困難になりそうな患者さんや情報共有をしておきたい患者さんをピックアップしてカンファレンスをします。看護師だけでなく理学療法士や作業療法士、言語聴覚療法士、ケースワーカーなど様々な職種で行います。
カルテの記録では分からないリハビリテーションの様子や看護師には見せない患者さんの態度や発言、ご家族の反応などから、より深く詳しく患者さんのことを知ることが出来ます。カンファレンスでの多職種からの意見を参考に、今後の方向性や看護師にできるアプローチの方法を考えていきます。患者さんの生活背景や性格なども考慮して、できるだけご本人またはご家族のニーズに合うような退院支援ができれば良いなと思います。
みどり病院での3年間の業務経験を通じて、地域包括ケア病棟に慣れてきました。知識や経験はまだまだですが、一人一人の患者さんに向き合い、医療だけでなく、暮らし、人生といった側面からも寄り添える看護を実践できるよう、頑張っていきたいと思います。