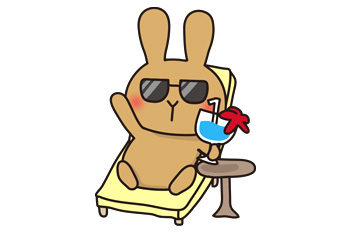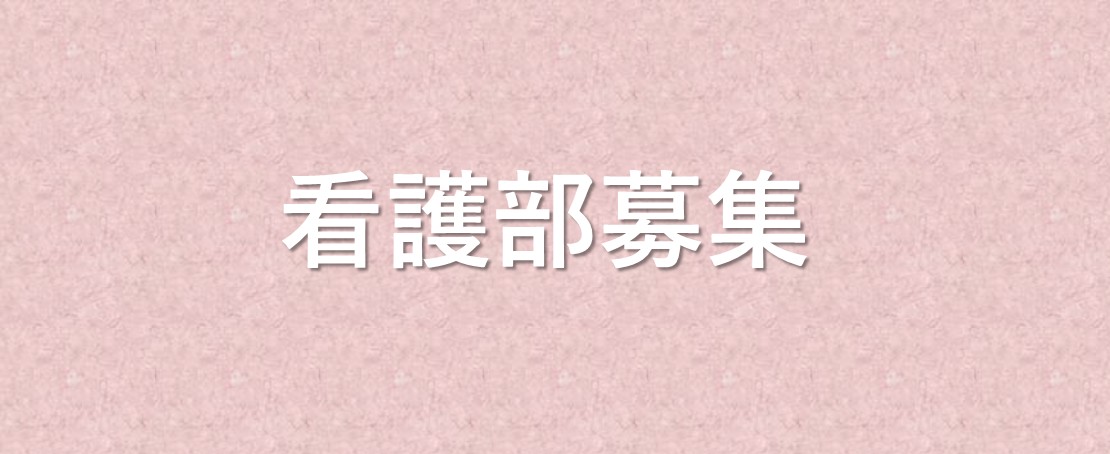今年の夏は特に異常な猛暑が続きましたね。毎年記録的な暑さを更新したとニュースでも発表されていますが、私自身としては今年は特に身体に堪える暑さだったと思います。その夏がやっと終わり、過ごしやすい秋がやってきました。秋と言えば、食欲の秋・芸術の秋・スポーツの秋と呼ばれますが、皆さんはどの秋がお好きですか?ちなみに私は食欲の秋が一番好きです。食べ物がおいしい季節であり、つい食べ過ぎてしまい胃もたれを起こしたこともあったり、なかったり(笑)
さて、これらの言葉がどういうきっかけで使われるようになったのか皆さんはご存知でしょうか?今回はこの3つの秋について、少し調べてみたのでご紹介したいと思います。
その1~芸術の秋とは何ぞや~

芸術の秋という言葉が一般的にうたわれるようになったのは、ある雑誌がきっかけだったと言われています。1918年に発行された雑誌『新潮』の中で、「美術の秋」という記載があったことから派生していることも、「芸術の秋」の由来とされ、加えて、秋には大きな美術展が続々と開催されます。※二科展、日展、院展など絵画・彫刻・工芸品などの芸術作品の大きな展覧会の開催が集中しているのも秋です。こうしたことからも「芸術の秋」といわれるようになったようです。
ちなみに、音楽会や美術展が秋に多い一つの理由としては、秋の天候が関係していると言われています。楽器や絵画、漆器などの芸術品は湿気に大変弱いデリケートなもので、楽器の場合は湿気による音程の狂い、芸術品ではカビなどで傷んでしまうことがあります。
そのため、夏のような暑さや湿気が多い時期を避けて、気候が落ち着いた秋の時期に集中して開催されることが多いと考えられています。
※
二科展:公益社団法人二科会が開催する美術展
日展:公益社団法人日展が開催する日本最大の総合美術展覧会
院展:公益財団法人日本美術院が開催する美術展
その2~スポーツの秋とは何ぞや~

「スポーツの秋」と注目されるようになったのは、1964年の戦後日本の復興の象徴として、国民の希望となった東京オリンピックです。東京オリンピックの開会式は10月10日に行われたのですが、この時期の東京は晴天になる確率が高い日だったこともあり、この日に開会式が設定された経緯があります。そして、1966年からは東京オリンピック開催にちなんで、「体育の日」が国民の祝日として制定。そんな体育の日ですが、「国民がスポーツに親しみ、健康な心身を培う日」というねらいが定められているのをご存じですか? つまり、日本のスポーツ界にとって非常に大事な日であり、同時にスポーツをしやすい天候に恵まれた日でもあることから、「スポーツの秋」がうたわれていったと言われています。
その3~食欲の秋とは何ぞや?~
美味しい食べ物がたくさん手に入る季節ということで、とくに違和感なく食欲の秋という言葉を受け入れられる人も多いと思いますが、食欲の秋の由来は以下の理由によるものと考えられています。
★また、食欲の秋の言葉の起源とされているのが、「天高く馬肥ゆる秋」という言葉です。元々は中国の人々が騎馬民族の匈奴が秋に襲来することを恐れて使っていた言葉でした。現在では、秋の快い気候や草を食んで肥えた馬の姿から収穫が期待できる時期として使われています。ついつい食べたくなるおいしそうな食材がたくさんある秋。食欲に勝つのはなかなか大変ですが、食べ過ぎには十分ご注意ください。
★秋の味覚の豆知識
秋が旬の野菜や魚、きのこなどを使ったさまざまな郷土料理が全国各地にあるかと思いますが、その中でも有名な郷土料理をあげてみました。旅行などで行かれる機会があれば、ご飲食されてみてはいかがでしょうか。
~まとめ~
秋は何をするにも心地よい気候のため、「食欲の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」といった言葉が続々と誕生してきたと思います。食べ物がおいしい季節でもあり、読書や絵画などに集中しやすい季節でもあり、身体を動かしてリフレッシュしやすい季節と、秋が一番過ごしやすい季節ではないでしょうか。気候が穏やかな秋の間に何か新しいことを始めて、皆さんの暮らしが益々すこやかになることを願ってます。
参考サイト