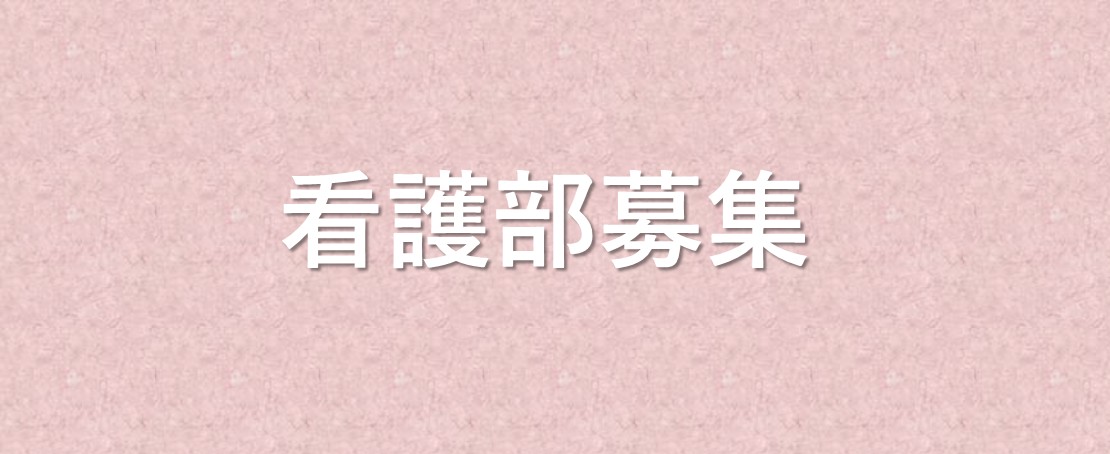軟膏や湿布などの、いわゆる「肌に使う外用剤」はNSAIDsなどの薬効成分である主剤(main agent)と、それ以外の基剤(base)から構成されています。基剤の性質によって、薬の効きやすさや副作用の出やすさ、使用感などに大きな違いが出ます。
日本薬局方製剤総則において、「皮膚などに適用する製剤」は剤形別に外用固形剤、外用液剤、スプレー剤、軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、貼付剤に分類されています。(※なお、この定義には局所に働くものだけでなく、皮膚を通して有効成分を全身循環血流に送達させることを目的とした経皮吸収型製剤も含まれます。)
外用固形剤
外用固形剤は皮膚に塗布又は散布する固形の製剤です。
固形を塗る、というとピンと来ないかもしれませんが、この定義には粉末状の個体である外用散剤が含まれます。(例:カデックス外用散®)
外用液剤
外用液剤は、皮膚(頭皮を含む)又は爪に塗布する液状の製剤で、リニメント剤及びローション剤があります。
リニメント剤は、皮膚にすり込んで用いる液状又は泥状の外用液剤で、フェノール・亜鉛華リニメント等があります。
ローション剤は、「有効成分を水性の液に溶解又は乳化若しくは微細に分散させた外用液剤である」とされます。
スプレー剤
スプレー剤はガススプレー方式のエアゾール剤と、ポンプにより噴霧するポンプスプレー剤に分かれます。
ゲル剤
ゲル剤は、皮膚に塗布するゲル状の製剤であり、水性ゲル剤及び油性ゲル剤があります。
軟膏剤、クリーム剤、貼付剤
軟膏剤とクリーム剤や、貼付剤(パップ、テープ)は同じ薬効成分でも複数の剤形が存在することが多く、使い分けに悩む場面もあると思うので、この二つの違いについて少し詳しく言及したいと思います。
<軟膏とクリーム剤の違い>
軟膏は、「皮膚に塗布する、有効成分を基剤に溶解又は分散させた半固形の製剤」と定義されており、油脂性軟膏と水溶性軟膏に分類されます。
油脂性軟膏がいわゆる最も基本的な「軟膏」で、基剤としては鉱物性の白色ワセリン、パラフィン、プラスチベース、シリコン、動植物性の単軟膏などがあります。
水分を吸収しにくく、皮膚保護作用が強く、基剤自体に軟化、消炎作用があります。
皮膚の刺激性も低いため、様々な皮膚疾患に用いることができます。
短所は主剤の皮膚浸透性が低いこと、水洗除去が困難なこと、ベトつきが気になる場合があることです。
水溶性基剤は主にマクロゴール軟膏が用いられています。
滲出液を容易に吸収するため、びらんに適した基剤です。
また、簡単に水で洗い流すことができます。短所としては、主剤の皮膚浸透性が低いこと、皮膚を過剰に乾燥させる恐れがあることです。
クリーム剤は「皮膚に塗布する、水中油型又は油中水型に乳化した半固形の製剤である」と定義されています。
つまり、界面活性剤を加えて、油と水の成分を混合する「乳化」を行ったものがクリーム剤なのです。
軟膏より主剤の経皮吸収性に優れ、べとつかず、水で洗い流せるのが利点です。
しかし皮膚刺激性が高く、また患部に滲出液を再吸収させてしまう可能性があるため、びらん・湿潤面などには向きません。
油中水型(W/O)は塗布すると冷たい感触があることからコールドタイプと呼ばれます。
一方、水中油型(O/W)はバニシングタイプと呼ばれます。
塗布した後、連続相の水分が蒸発して消えたように見えることからそう呼ぶのですが、使用感が良い反面、薬を塗った実感に乏しく、過剰使用になってしまうことがあります。
ざっくり言うと、軟膏のほうが油っぽく、肌に優しいが使用感が悪い、クリームのほうが水っぽく、使用感が良いが肌を刺激するということになります。
なお、一様にクリームは創傷部に使わないかというと、必ずしもそうではありません。
例として、ゲーベン®クリームは褥瘡部に使用されています。
使い分けの例として、代表的な保湿剤の「ヘパリン類似物質」の外用剤について取り上げてみます。
先発品として、ヒルドイドクリーム®、ヒルドイドソフト軟膏®、ヒルドイドローション®、ヒルドイドゲル®、エアゾール剤のヒルドイドフォーム®という多様な剤形が存在します。
なお、「ヒルドイドソフト軟膏®」は名前に軟膏と入っていますが現在の薬局方の規定においては、油中水型の「クリーム剤」に分類されます。
「ヒルドイドクリーム®」は水中油型のクリーム剤です。
薬局方において、「油中水型に乳化した親油性の製剤については油性クリーム剤と称することができる」という記載があり、ヒルドイドソフト軟膏の一般名は「ヘパリン類似物質油性クリーム」となっております。
ヒルドイドクリームは「ヘパリン類似物質クリーム」です。
外用剤はこのように名前と実際の剤形が一致しない場合があるので、使う時には何の基剤が使われているのかを確認してみましょう。
クリームよりソフト軟膏のほうが油っぽいため、皮膚保護作用が強く、重症例や乾燥する冬場には向いています。
塗るとテカリがあるため、あまり顔面へは使用しません。ローションやフォームは伸びがよく、広範囲に使用したいときに向いています。
同一人物に対して、手はソフト軟膏、顔面はクリーム、頭はローションといった具合に使い分けることも珍しくありません。(※なお、主成分のヘパリン類似物質自体に血の巡りを良くする作用があり、出血を助長する可能性があるため基剤関係なく創傷部には適していません。)
これらは保管するときにも注意する点が違います。
外用剤を冷蔵庫で保管する人もいると思いますが、ヒルドイドローションは冷蔵庫に保管してはいけません。
ごくまれにですが、低温条件下だとローション内の成分が結晶化して析出することがあるためです。
フォーム剤は高温条件下だと破裂する恐れがあるため、直射日光の当たる場所や火気の近くは避けてください。
また、ヒルドイドはステロイド剤と混合処方することも多く、混合したあとの配合変化についても留意しておく必要があります。
一例として、ボアラ軟膏とヒルドイドソフト軟膏を1:1で混合した場合、常温で8週間は安定しますが、ソフト軟膏ではなくヒルドイドクリームと混合した場合は常温では主剤の含量が低下するため、要冷所保存となっています(軟膏・クリーム配合変化ハンドブック第2版参照)
原則として外用剤は単剤での使用が推奨されています。
異なるクリームや軟膏を混合した場合、経皮吸収や保存性などが、どのように変化するのか予想がつかないことがあるためです。
ですが実際は、患者のアドヒアランス向上のため、複数の外用剤を混合することは珍しくありません。

<パップ剤とテープ剤の違い>
貼付剤、いわゆる湿布薬はパップ剤とテープ剤の二種類に分類されます。
Papは、元々は泥状に製した塗り薬のことを指していました。
昔は適宜、使用時に泥状の薬を布に伸ばして湿布として使用していたのです。
現在のパップ剤は、あらかじめ薬剤と布を一体化して簡単に使えるように成形しており、「成形パップ」と言われます。
現在の日本薬局方においては、「パップ剤は、水を含む基剤を用いる貼付剤である、テープ剤は、ほとんど水を含まない基剤を用いる貼付剤である。」と定義されています。
つまり、この2剤形の違いは「水分の有無」なのです。
水分を含むため、パップ剤は貼った際に気化熱を奪い、ひんやりする感覚があります。(※トウガラシ成分のカプサイシンなどを含んだ温湿布というものがありますが、水分を含んでいるのは同じなので、貼付した際は同様に気化熱を奪います。)
テープ剤のほうが軽く、薄く、剥がれにくいですが、逆に言うと貼りつく力が強い分、パップ剤よりもかぶれやすい傾向があります。
よって、関節部位など、よく動き、剥がれやすい部位には吸着力の強いテープ剤を使い、皮膚が弱い人に使用する場合はパップ剤を用いるなどの適切な使い分けが必要です。
<モーラス®テープとモーラス®パップの違い>
経皮鎮痛消炎剤であるケトプロフェンの外用剤、モーラス®テープとモーラス®パップを比べてみます。
パップ剤のほうがテープ剤より経皮吸収性が劣るため、用法はテープが1日1回、パップが1日2回となっています。
また、相互作用の注意点にも違いがあります。
テープの添付文書には経口のメトトレキサートとの相互作用が記載されていますが、パップにはありません。
これは薬効成分の吸収量の差によるものです。
2015年には、モーラス®パップXRが発売されました。
この製剤は、パップ剤であるのにモーラス®テープと同等の角層中濃度を保つことができるので1日1回の貼付が可能です。
又パップ剤であるため水分を保つことが可能なのに、粘着力が持続します。
つまりパップ剤とテープ剤の良いとこ取りをしたような剤形なのです。
11月頃は日増しに寒くなり、乾燥による肌荒れも気になる季節です。
患者さんに合った外用剤は何か、薬効成分だけでなく基剤にも注目して考えていきましょう。