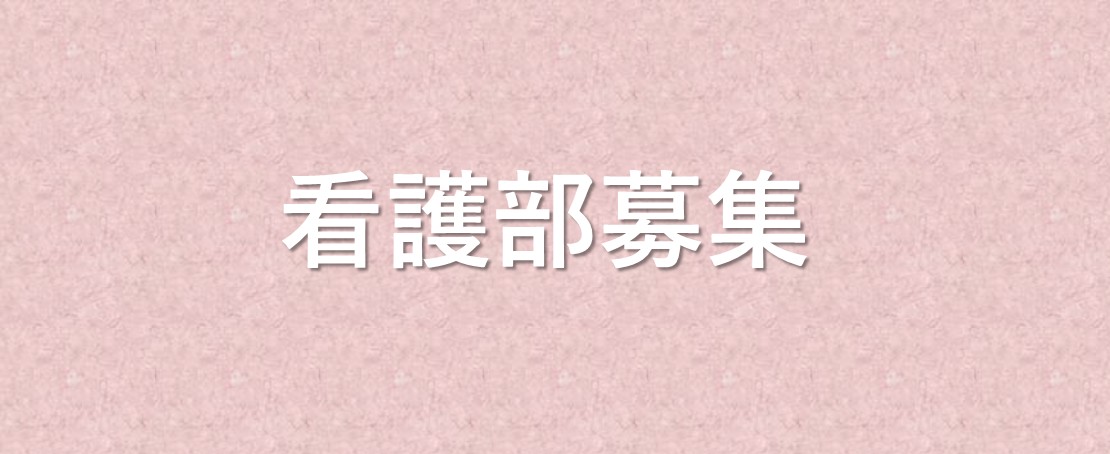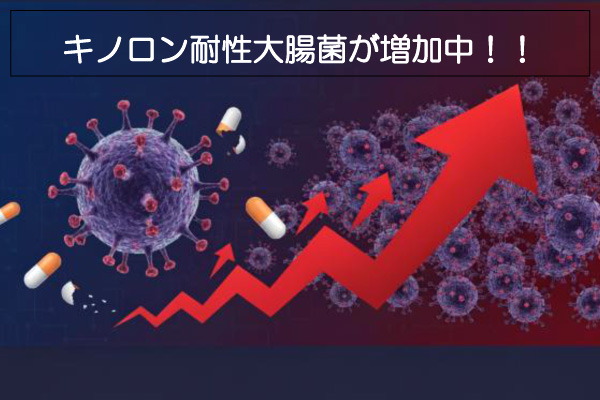
■はじめに
かつて「切れ味の良い抗菌薬」として一世を風靡したキノロン系抗菌薬。しかし、今やその評価は大きく変わろうとしています。特に膀胱炎などの尿路感染症において、キノロン系を第一選択に使うことは「原則NG」とされる時代が到来しています。その背景には、大腸菌におけるキノロン耐性の急増と、それに伴う抗菌薬治療の失敗例の増加があります。
■キノロン系抗菌薬とは?
キノロン系抗菌薬は、細菌のDNA複製を阻害することで強い殺菌作用を持つ薬剤群であり、レボフロキサシンやシプロフロキサシンなどが代表的です。広範囲に効くため、かつては膀胱炎など軽症の感染症にも積極的に使用されてきました。
ところが、その便利さがあだとなり、過剰使用・不適切使用によって耐性菌の急増を引き起こしました。特に大腸菌(E. coli)は、尿路感染症の主因菌でありながら、キノロン耐性を獲得しやすい菌として知られています。
■世界に広がるキノロン耐性大腸菌
近年、WHO(世界保健機関)やCDC(米国疾病予防管理センター)などが警鐘を鳴らしているのが、キノロン耐性大腸菌の世界的拡大です。
2017年にWHOが発表した「薬剤耐性菌の優先度リスト」でも、キノロン耐性を有する大腸菌は「高優先度の耐性菌」として位置付けられ、特に発展途上国では、市販薬としてキノロン系が容易に手に入る環境も相まって、耐性菌が急増しています。
たとえばアジアの一部地域では、尿路感染症由来の大腸菌の50~70%がキノロン耐性という報告もあり、これらの地域からの渡航者が耐性菌を持ち込むケースも問題視されています。
■日本における耐性状況
日本でも例外ではありません。2007年の時点で、日本における大腸菌に対するレボフロキサシン(フルオロキノロン)耐性率は約24%でしたが、2020年には約41.5%まで上昇しています。
特に、高齢者や再発性膀胱炎の患者、あるいは過去にキノロン系を繰り返し使用したことのある人では、耐性菌の保菌率が高い傾向にあります。
さらに、感染症治療においては「経験的治療(Empiric Therapy)」として抗菌薬を選択する場面が多く、耐性菌の存在を見落としてしまうと初期治療の失敗を引き起こす危険もあります。

■なぜ膀胱炎にキノロンが「NG」なのか?
その理由は、大きく以下の3点に集約されます。
(1)キノロン耐性大腸菌の増加
前述の通り、キノロン耐性大腸菌の頻度が高いため、膀胱炎に対してキノロン系を使っても効かない可能性が高いという問題があります。治療の遅れは、腎盂腎炎などの上部尿路感染症への進展を招く恐れもあります。
(2)副作用リスクが高い
キノロン系抗菌薬には、腱障害(アキレス腱断裂など)や中枢神経障害(痙攣、幻覚、せん妄など)、血糖異常といった重篤な副作用も知られています。FDA(米国食品医薬品局)は2016年に、「単純性尿路感染症のような軽度感染症には使用を控えるべき」と明確な警告を発しています。
(3)重要な抗菌薬として温存すべき
キノロン系は、呼吸器感染症や複雑性尿路感染症、敗血症など、より重篤な感染症への備えとして温存すべき薬剤です。軽症疾患に濫用されることで、貴重な治療オプションを失うリスクがあるのです。
■現在の膀胱炎治療の推奨薬は?
日本化学療法学会や感染症学会のガイドラインでは、膀胱炎に対しては以下のような抗菌薬が推奨されています。
- ホスホマイシン(FOM):単回投与で効果が期待でき、耐性化も比較的少ない
- セフェム系(例:セファレキシン):第一世代の経口剤
- スルファメトキサゾール・トリメトプリム(ST合剤):使用歴に注意
いずれも、患者の既往歴や地域の耐性率を考慮しながら選択されるべきであり、特に再発性や高齢者では尿培養の実施が重要です。
■まとめ:キノロン系は「最後の砦」、むやみに使わない
膀胱炎に対してキノロン系を「とりあえず使う」時代は終わりました。医療者としての責任は、目の前の患者を治療することだけでなく、未来の感染症治療を守ることでもあります。
抗菌薬の選択は、単に「効く薬」ではなく、「最も適切な薬」を選ぶことが重要です。
キノロン系は、いざという時の「切り札」として温存し、膀胱炎のような軽症例には適正使用を心がけるべきでしょう。